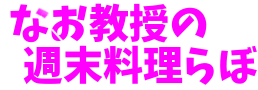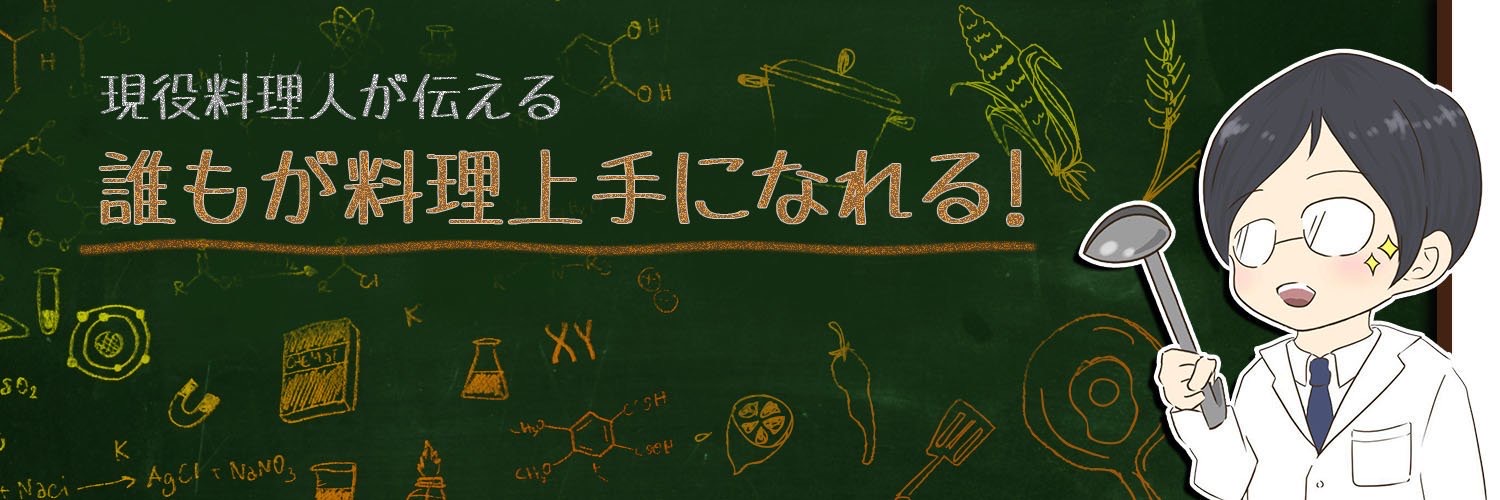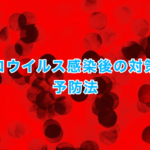こんにちは!なおです。
今回は「鶏のもも肉を焼く」がテーマです。

鶏肉はスーパーで簡単に手に入り、価格も安定していてよく使う食材ですよね。よく使うからこそ食材のことを詳しく知っておけば料理のレベルは確実に上がります。
要点は異なる2つのパーツで構成されているというところです。では解説していきます。
_φ(・_・ もくじ
鶏もも肉:皮
皮の特徴を知り調理に活かす
鶏の皮はそれ自体もかなりの脂肪で構成されており、皮と身の間にも脂肪が蓄えられています。
なので、「脂肪分を活かす」か「脂肪分を溶かし出す」の両極端に振れた調理をすると美味しさが意図的にクローズアップされ、食べてに好感触として伝わります。
居酒屋さんや焼き鳥屋さんでも鶏の皮の料理はたくさんありますが、どれもこの両極端のテクスチャーで美味しさを表現していますね。
- 茹でで薬味とポン酢で(脂肪分を活かす)
- カリカリに焼くor揚げる(脂肪分を溶かし出す)

今回は「鶏のもも肉を焼く」がテーマなので②番目の「脂肪分を溶かし出す」をやっていきます。
鶏の皮を焼く
フライパンに少量の油を引きます*これには以下の理由があります
- 皮の表面は歪であり平らではないので鍋底面と皮の隙間を埋め、鍋底の熱が効果的に皮を熱するように。
- 油は高温から低温に移動しようとする性質があるため*皮の脂が加熱で溶けたあと皮内部から効果的に外へ移動させるため。
油を引かなくても加熱はされますが引くほうが効果は早く現れます。

焼いていくと脂が排出されると同時に縮んできます。適宜油を捨てながら加熱を進めます。
求める食感は?
ここで皮の形が変形し、脂分が減ることによって硬くなってきますね。となると、鍋底にピッタリ張り付いてくれなくなってきました。どうしましょう。以下の二択です。
- 皮のパリッとしたテクスチャーを意図的に求める(身側の食感は少し諦める)
- 身のジューシーなテクスチャーを意図的に求める(皮側の食感は少し諦める)
字数が一緒になりましたw。今日は何かいいことがあるかもしれません。
どちらを選択しても美味しさの王道である「外はカリッと中はジューシー」という食感のコントラストは成立しますので、プロでも各お店によって(各シェフによって)考え方や最終形態の理想形が異なります。
選択の結果、調理工程はこうなります。
- 身側から重しや自力で押さえ、強制的に皮を平にしながら加熱(大きな一枚で焼く時など)
- 皮側の加熱は身側にストレスをかけないように少々傾けたりしながら加熱(一口大カット)
もちろん大きな一枚で焼く時も2の工程でやるとより身のジューシー感を感じられ、しかも一枚を自分で切りながら食べることでリッチな気分も味わえます。
一枚で焼くかカットして焼くかは、焼き方の違いもあれどそれよりも重要な食べ手の印象も違うのです。そこもイメージして料理するのが上達への近道かもしれませんね。

ここで大切なのは「しつこく焼く」ことです。
焼く目的ははっきりとしていて「脂肪分を溶かし出す」ことなので、溶け出て硬くなるまでしつこく根気よくやるのが大事です。中〜弱火です。といっても慣れてきたらほったらかしでもいけます。たまにチラッとみてトングなどでチョンチョンと触って確認しましょう。もちろん焦がしてしまってはダメですよ。
脂が溶けきるのと焼き色がつくのを同時に終了できたらいいのですが、ちょっと誤差が生まれます。その誤差を埋めるのはやはり経験でしかないです。やることはシンプルに「火の調節」だけですので、そのうち誰でもできるようになりますよ。fight!!