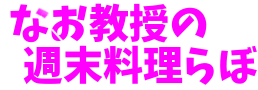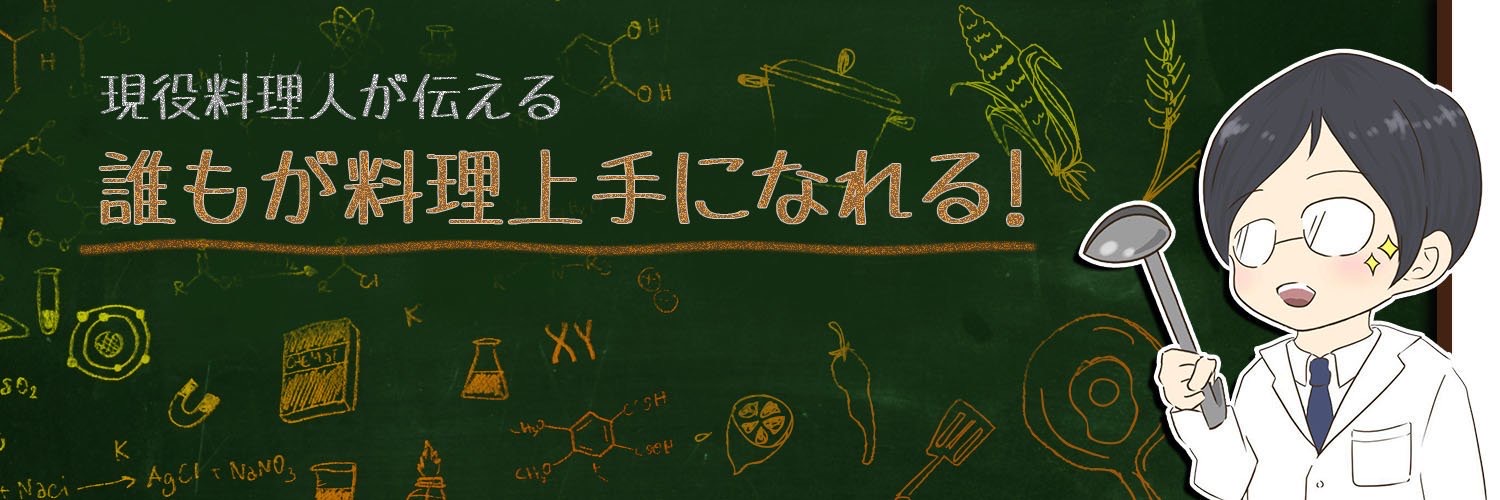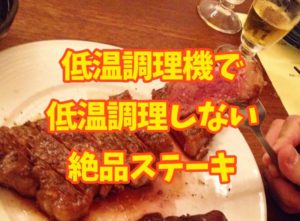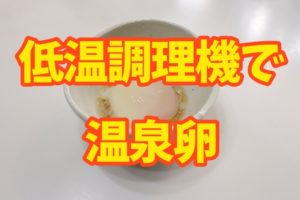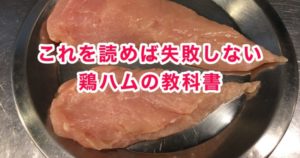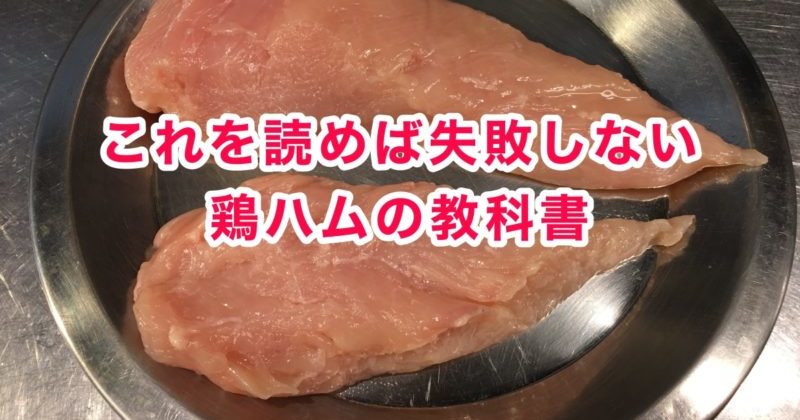
最近では低温調理の器具が家庭用でたくさん販売されていますね。(BONIQ、ANOVAなど)
現在ではおうちで手軽に低温調理が楽しめます。ですが調理師の視点で見ると、衛生の知識が全くない状態で挑むとなかなか危険だな!と思っております。(ちなみにBONIQのホームページには55度を推奨しています)
絶対に食中毒が出ないように料理しないと、せっかく美味しく作っても意味ないですからね。
低温調理は今では手軽にできるようになりましたが、みなさん衛生の知識は十分にありますか?
食中毒と隣り合わせの低温調理ですが「パスチャライズ」を行うことを念頭に置いて調理作業することで、安全かつ美味しい最高の料理になります。

(過去1回経験あり)
この記事は「鶏胸肉の低温調理」の安全な方法を科学と衛生の観点からまとめたものです。
- 63℃で8分42秒
- 60℃で35分
- 57.8℃で1時間21分24秒

カンピロバクターはサルモネラ菌よりも弱いのでこれを実践するとカンピロバクターもやっつけられますよ!
_φ(・_・ もくじ
鶏ハムの低温調理|まずは下処理

とりあえず鶏ハムの基本的な作り方をシンプルに解説していきますね。
このページに到達している皆さんのほとんどがすでにお分かりだと思いますが、塩して低温調理機に任せるだけです。大事なことは時間と温度。
まずは下の囲みをご覧ください。
- 鶏胸肉の掃除をする
- 下味をつける
- 袋に入れ、湯煎で低温調理する
大まかに3つの工程があります。なんだか簡単そうですね!

鶏胸肉の掃除をする
鶏ハムに適しているのは【胸肉】です。
もも肉でもできそうですがハムっぽい食感にならないし、もも肉ならもっと美味しくなる調理法があるのでわざわざ低温調理してハムにする必要性がないです。
もちろん何か食材を巻き込んで成形して低温調理する場合はありますが、脂や皮はハムに必要ない要素なので提供時に工夫が必要です。
そして鶏肉ですが、すでに菌汚染されていると思ってください。(近年では筋肉中にも食中毒菌が検出されています)
これを念頭において作業を進めます。
余分な部分を取り除く

胸肉には皮がついていますが、今回の調理には不要です。皮は手で簡単に剥がせます。
皮を取り除いたらその面を下にしておいてください。
そうすると胸肉は大きい部分と小さい部分で構成されているのが分かります。

この大きい部分と小さい部分を切り分けてください。
境目にスジがあるのでこれも取っておきましょう。
大きい部分は形が綺麗で調理後の見栄えも良いのでハムに適している部分です。
目視できる血管は全て取り除いてください。その理由は後述します。
毛抜きなどを使うと簡単です。

小さい部分は中に太めの血管が入っているので、縦に切り込んで開いて取り除いてください。
太い血管から枝分かれしているものもあるので全て取り除きますが、開いてしまうと元どおりにはなりません。
それでもいいならハムに、見た目を気にするなら他の料理に使ってください。
なぜ「血管、血管」とうるさく言うのかというと、
今回の低温調理は血液が凝固しない温度で行うので「赤い斑点」や「赤く染まった部分」ができてしまいます。
もちろん食べても問題ないようにはなるのですが、見た目が気持ち悪いので取り除きます。


余談ですが、血液も血管も大腸菌類の汚染確率が高い場所です。
鶏肉の場合は食肉処理場ですでに筋肉部分にも汚染が広がっているのが一般的ですので血管をとったとしても別に...ですがより危険因子を減らすと言う意味での作業です。
こういった作業を日頃から行っていると衛生的に作業しようという心構えができて、より料理のクオリティが上がります。
下味をつける
塩をします。お好みの量で結構です。
基本は重さの1%。本来のハムは保存目的なのでもっと塩分が高いのですが、おうちで冷蔵庫保管して早めに消費するという前提なので、食べていい感じの塩分でいいと思います。
ここで重要なのが、袋かラップで一晩おいて塩分を浸透させます。浸透させることによって浸透圧で水分が外に出てきますが、これはジューシーさが損なわれるほどの量ではないのでご心配なく。
1晩置くと肉質が少し透き通ったような色に変わり、保水効果が出ます。
袋に入れ、低温調理する

翌日水分を拭き取り、ドライハーブやスパイスをまぶし(お好みで)
肉を袋に入れ一緒に少量の油を入れます。
このあと袋ごと水につけて中の空気を押し出すのですが、どうしても真空状態にはなりません。
空気が肉と袋の間に残っていると温度伝達の妨げになるので(空気は熱伝導率が悪い)より密着度を高める狙いで油を入れるのです。
さあ、いよいよスイッチオンですがここで問題の『温度』ですね。

それは後ほど解説しますね。
カンピロバクターをパスチャライズできる温度と時間

ここで牛肉の低温調理と比較してみよう
ここで牛肉と比較してみましょう。
牛肉の塊肉を低温調理しローストビーフなどを作ると仮定すると、鶏胸肉の鶏ハムとは何が違うのでしょうか?
| 鶏胸肉の鶏ハム | 牛肉のローストビーフ | |
| 菌危険度 | 高(主にカンピロバクター、サルモネラ菌) | 低(主に大腸菌類) |
| 菌汚染度 | 高 | 低 |
| 低温調理後の作業 | なし | 表面を高温焼成 |
このように結構危険度高めなんですよね。
カンピロバクターは少量の摂取で発症する強力な菌ですので、本当に注意が必要です。
もし殺菌しきれていなかったら袋から出したところから二次汚染は広がっていきますので、非常に危ない状況だと言えます。
低温調理での完全殺菌をゴールとして調理を進めていきましょう。
〇〇℃で〇〇分?
保健所や厚生労働省からは「十分に加熱せよ」ということしか発信がなく、一体カンピロバクターは何度で死ぬのかは公に出ているデータは簡単にはわかりません。
いくつか漁ってみましたので引用しながら解説していきます。
中心部の温度が75℃以上、1分間以上の加熱で死滅します
一般財団法人 食品分析開発センターSUNATEC
微生物検査室
ここでいう温度は「中心の温度」ですので、表面温度とは異なります。1分以上の加熱とありますが、75℃だとほぼ即死します。

「カンピロバクターの熱抵抗性は大腸菌よりやや弱く、牛乳中で72℃、20秒または60℃、80秒間で死滅する」
『新・食品衛生学』藤井 建夫/著
カンピロバクターは60℃で80秒という具体的かつ驚愕な数値が出てきました。
カンピロバクターは大腸菌よりも弱いともあります。かなり凶悪な菌ですが割と早めに死んでくれますね。
カンピロバクターが死ぬ温度と時間はわかりました。では鶏肉内のその他の菌はどうなのでしょうか。大腸菌やサルモネラ菌ですね。

サルモネラ菌は71℃に加熱すると即座に死滅する。
サルモネラ菌をパスチャライゼーションするには、
71℃で即時、68℃で15秒、66℃で2分42秒、63℃で8分24秒の保持時間が必要である。
『Cooking for Geeks 料理の科学と実践レシピ』Jeff Potter/著
Cooking for Geeksではさらに「米国農務省(USDA)」のガイドラインを元にさらにわかりやすくまとめられています。
なるほど、カンピロバクターとサルモネラ菌、大腸菌を死滅させるには
サルモネラ菌のパスチャライゼーション保持時間に準ずるのが良いということがわかりましたね。

なのでサルモネラ菌をパスチャライズすると良い!
もう一度言いますが、ここに出てくる温度は全て「中心の温度」ですので、
肉全体がその温度になり、かつその温度を保持時間分維持し続けることが前提です。
また著書内のグラフでは「USAD FSISによる、鶏肉を調理する際の保持時間」と題して
60℃35分、57.8℃で1時間21分24秒と具体的な保持時間も公表されています。
これが正しい温度と時間だ!
- 63℃で8分42秒
- 60℃で35分
- 57.8℃で1時間21分24秒
そして著者はこのように締めくくっています。
パスチャライゼーションは滅菌とは違い、病原体を安全なレベルにまで減少させることしか意味していない。
病原体のレベルは低下するがゼロになるとは限らないので、生育温度になれば再び危険なレベルにまで戻ってしまうかもしれない。
『Cooking for Geeks 料理の科学と実践レシピ』Jeff Potter/著

以上が殺菌(パスチャライゼーション)の視点からみた鶏ハムです。
もちろん低い温度で加熱する理由はみなさんご存知の通り、「タンパク質を過度に硬くさせないように」です。その温度を守りながら安全を確保して初めて料理として成立するのです。
水から入れる?お湯から入れる?

ここまでの解説で鶏肉に最適な保持時間と温度はわかりましたね。
ではここであと一つの疑問点についてみていきましょう。

そうです。一体袋をいつ投入するのか問題です。
これにはちょっとした理由がありますので、わかりやすく解説していきますね。
実は危険な低温調理
かなり突っ込みますが、「菌が活発になる温度帯」を早く過ぎるのが調理理論では定石となっています。
ですが低温調理の場合、設定温度を間違うとただの「菌の増殖環境維持装置」となってしまいます。
そんな恐怖の低温調理機でもパスチャライゼーションという低温殺菌行為で無敵に!というわけにもいかないんですが。それには「毒素」が関係してくるのです。
菌自体はパスチャライズされてなくなりますが、活発活動温度帯が長引いてその菌がたくさん増殖している時、有害毒素を生成するという可能性があるのです。
毒素は加熱にも強く、すでに菌ではないためパスチャライゼーションの対象外となります。
ですので素早く目的温度に肉自体の温度を到達させないと危険だということです。
温度設定と開始のタイミング
例えば「水からスイッチオン」した場合、肉の中心部が目的温度に達するまで時間がかかりますよね。
逆に「目的温度になってから始める」場合は上の方法より早くなることはおわかりだと思います。
Cooking for Geeksでは「食材温度を2時間以内に58℃以上にして、その後任意のパスチャライゼーション保持時間を保つ」とあります。
ということで、肉の袋を入れる前にスイッチオンしておいて目的の温度になったら袋を入れて中心温度を目的値まで到達させ、それに応じた保持時間分温度を保つというのがより安全な方法です。
どうせ中心温度を保持時間分維持するだけなのだからと言って、毒素を発生させないようにしなければならないのですね。
鶏ハム作り方まとめ
- 鶏胸肉から血管除去
- 塩して一晩
- 袋に入れ、ハーブやオイルも入れる
- 器具のスイッチオンして目的温度になるまで待つ(60℃)
- なったら湯煎開始
- 保持時間まで他のことやっとく(肉の中心に温度が到達してから35分保持)
低温調理にあると便利なグッズ
ちなみに袋ですが、別にジップロックでもなんでもいいのですが、それなりにしなやかな素材でなければ空気が抜けきらない場合があるので注意してくださいね。
あのスーパーのレジ通り抜けたところの机にあるでしょ?長いロールにめっちゃ巻かれたしゃらしゃらの袋。あれが実は一番適しています。もちろんスーパーから拝借するんじゃなくて、福助工業の「フクレックス」というのを愛用しています。熱にも強いポリエチレンでピンホールは今まで一度もありません。それに安い!
ちなみに貝印製の低温調理機はシーラー付きです!
貝印のページを見に行くここでもう一つオススメの中心温度計を紹介します
この中心温度計の優れている点はなんと言っても「針の直径が小さい」こと。
0.1mm変わるだけで挿し心地は随分変わります。肉へのダメージも少ない方がいいですよね。
湯や油の温度も測れるのでいいですよ。
美味しく安全に作るには、肉自体の温度が何度なのかを把握することが大事だとわかっていますので、数字で見ることは感覚を養うのにも一役です。
肉を焼くには是非持っておきたい道具ですね。
他にも便利な道具はあるのですがまた別の機会に。
安全に低温調理機を利用して料理の幅を広げていってくださいね!
今回もありがとうございました!

低温調理は理屈は分かっていても、
温度や時間を間違うととても危険です。
今回は低温殺菌(パスチャライズ)の観点から、
温度と時間を考えてみました。
みなさんの料理に活かせていただけたら嬉しいです!
ありがとうございました!
- 【オーバーナイト低温調理】牛ほほ肉の赤ワイン煮込み|肉の味とアルコール
- 低温調理器のこんな便利な使い方|解凍めちゃはや爆速解凍マシーン
- 低温調理機を使った砂肝とハツのコンフィ:カンピロバクター のパスチャライズの温度と時間
- 低温調理機ANOVAを3台使った僕が買ってはいけない理由を語ります。
- 低温調理機を使った低温調理しないステーキの調理法解説:いいとこ取りで最上級のステーキを再現
- 鶏レバーパテを安全に低温調理する温度と時間:カンピロバクターのパスチャライズ
- ローストビーフの低温調理の温度と時間:赤身肉の塊を柔らかくローストする方法
- 【温泉卵完全版】低温調理機での作り方|温度と時間
- 鶏胸肉を安全に低温調理する温度と時間:自作【鶏ハム】【サラダチキン】:カンピロバクターの低温殺菌パスチャライズ
- BONIQの落とし穴:本当にその温度で大丈夫?
anova BONIQ hajime pasta pickup salad sosa あさり からあげ アヒージョ イカ カダイフ クロックスビストロ コンフィ サラダ 野菜 ステーキ トマト 野菜 ナス ニョッキ ノロウイルス パスタ ベシャメルソース ホタルイカ マヨネーズ 野菜 メイラード反応 ローストビーフ 低温調理 唐揚げ 塩 揚げ物 椎茸 油 泡 温泉卵 焼く 牡蠣 生肉 豚肩ロース 野菜 食中毒 馬刺し 魚 魚料理 鶏むね肉 鶏肉